説明
詳細:
ジェズアルド・シックスによるクリスマス
何世紀にもわたり、クリスマスとその周辺の季節は作曲家たちに創造性の新たな高みへとインスピレーションを与えてきました。このプログラムは、チューダー朝教会の永遠の美しさから21世紀まで、時代を超えて、神秘と喜びを呼び起こす作品が選ばれています。
ルネサンス時代、キリストの降誕を祝うクリスマス前の数週間、アドベントは、驚きと内省の時でした。何世紀も昔のキャロルがこの物語を語り、いくつかの作品は受け継がれた形で、他の作品は熟練の編曲家によって新たに解釈されています。キリストの降誕に焦点を当てた作品がこのコレクションの骨格を形成しています。トーマス・ハーディによるクリスマスイブの情景を描いたタブローは特に印象的で、同時に、キリストの誕生を告げる音楽と並んで、イエスの生後数週間についての洞察が提示されています。テーマと形式は時代を超えて受け継がれています。2つの子守唄は、何世紀も離れて書かれたにもかかわらず、不安な子供たちに歌われるように、優しく歌われる繰り返しを用いています。最も優美なメロディーのいくつかは、マリアに捧げられた作品に見ることができます。
静寂と喜びに満ちた熱狂が織りなす、祝祭の雰囲気を少しでもお伝えできたら幸いです。これは私たちが心から歌いたい音楽です。毎年年末にこのレパートリーを聴くたびに、私たちは皆、ある種の魔法を感じます。
「ヴェニ・エマヌエル」は中世に遡る待降節の賛美歌で、クリスマス前の数週間に用いられた平唱アンティフォナに起源を持つ。「おお、来てください、エマヌエル」という英語訳で、救世主の到来を告げるこの賛美歌は多くの人に知られている。フィリップ・ローソンによる編曲は、聖歌を基調としたこの旋律に敬意を表し、伴奏部分の繊細な作法が、馴染み深い旋律を優しく支えている。
ドイツの作曲家で理論家のミヒャエル・プレトリウスは、同世代の作曲家の中でも最も多才で多作な作家の一人だが、プロテスタントの賛美歌の編曲で最もよく知られているかもしれない。「Nun komm, der Heiden Heiland a 6」は、マルティン・ルターによる賛美歌「Veni, redemptor gentium」の翻訳をテキストに採用し、模倣的なテクスチャと印象的な身振りで聴き手の注意を絶えず惹きつけ、劇的な修辞効果を生み出している。メロディーの新しい部分が現れるたびに、すぐに華やかさを増す一連の装飾音が続く。テクスチャーが絶えず書き換えられ、最後の行「Gott solch Geburt ihm bestellt」(「神が彼にこのような誕生を定めた」)で大きな衝撃がもたらされる。
オークニー諸島の詩人エドウィン・ミュアの詩に曲を付けた『受胎告知』は、2011年にイギリスの作曲家ジョナサン・ハーヴェイによって、ケンブリッジ大学セント・ジョンズ・カレッジの聖歌隊のために作曲されました。ハーヴェイはこれが自身の遺作になると信じていました。ハーヴェイは、エネルギーと静寂の相互作用を特に重視し、その核に一体性を持つ精神性の形を模索しました。このアプローチは、アドベントの季節における期待と内省の組み合わせに類似しています。各節の冒頭には、冒頭の言葉をさりげなく想起させる音楽的アイデアが導入されています。作品の中心にある静寂の瞬間「時を越えた羽根」は、後に再び捉えられ、最終節の「深まるトランス状態」が、美しい一連の終結和音によって生き生きと表現されます。
トーマス・タリスによる合唱による応答曲「Videte miraculum」は、平歌をソロラインとして用いると同時に、美しく織り込まれた6声のポリフォニックなテクスチャーへと溶け込ませています。特に印象的なのは、「miraculum」の冒頭の模倣部分(各声部の入りごとに繰り返される不協和音は催眠効果を生みます)と、「Et matrem」の輝かしいハーモニーです。このハーモニーは、戻ってくるたびに強度を増していくように見えます(この曲はメアリー1世が妊娠中に作曲されたと考えられていることも特筆に値します)。
シェリル・フランシス=ホードの「約束された生命の光」は、聖ベーダのラテン語のテキストに、聖ヨハネの黙示録の短い英語のフレーズ「我は輝く明けの明星なり」を引用している。和音の積み重ねを通して、声部は徐々に明らかになり、この効果は曲の最後でも繰り返される。中間部は、長くメリスマ的なボーカルラインによって彩られ、「aeternam」(永遠)という言葉が際立っている。
「喜びなさい」を意味するガウデーテは、待降節第三日曜日(「ガウデーテの日曜日」として知られる)にちなんで名付けられた中世のキャロルです。この歌は1582年頃、スカンジナビアの『Piae Cantiones』という書籍に初版が収録されました。各節のシンプルな旋律に、簡潔なリフレイン、つまり「重荷」が応えており、このバージョンではブライアン・ケイによってハーモニーが付けられています。
レイフ・ヴォーン・ウィリアムズは、数年かけて『イングリッシュ・ヒムナル』のために民謡を収集し、彼が敬愛するチューダー朝時代の作曲家たちのスタイルを反映したハーモニーで『天から送られた真実』を巧みに編曲しました。この歌詞とメロディーは後に『クリスマス・キャロルによる幻想曲』に用いられ、1912年にヘレフォード大聖堂で初演されました。最後の詩節では、オーウェイン・パークがこれらのハーモニーの一部をより現代的な視点で再解釈し、ヴォーン・ウィリアムズ自身の作品のコード進行を微妙に参照しています。
ドイツの賛美歌「Es ist ein Ros' entsprungen(邦題:バラは生ける)」は1599年に初めて印刷され、10年後にはミヒャエル・プレトリウスがハーモニーを奏でたメロディーに合わせて歌われるようになりました。最初の詩節は、エッサイの木の幹から芽吹くバラを描写しています。このイメージは中世に特に人気があり、当時の多くの宗教芸術作品に描かれていました。19世紀以降、他の詩節も加えられ、その多くは闇と悪を払う繊細な花の香りに焦点を当てています。
「アンジェラス・アド・ヴァージンム」は、13世紀後半から16世紀半ばにかけて、イギリス、フランス、アイルランドで少なくとも6つの写本に見られる中世の人気キャロルです。歌詞はラテン語(「アンジェラス・アド・ヴァージンム」)と英語(「ガブリエル・フロム・エヴェネ・キング」)の両方で登場し、それぞれの写本によってメロディーが微妙に異なります。天使ガブリエルがマリアを訪ねる物語を描いたこの詩全体は、もともとアルファベットの連続する文字で始まる27のスタンザから構成されていたと言われています。ここでは、より控えめな4つの詩節を演奏し、曲が進むにつれて徐々に声部を追加していきます。
「Lullay my liking(私の好きな子守唄)」は、グスタフ・ホルストがサックステッドの聖霊降臨祭のために作曲しました。このリフレインは、英語の子守唄の初期の例です。「lullaby(子守唄)」という言葉は、不機嫌な子供を落ち着かせるために使われる「lu lu」や「la la」、あるいは同様に古い時代の『コヴェントリー・キャロル』に見られる「bye bye(バイバイ)」といった音に由来すると考えられています。ホルストは各節を同じソプラノ独唱者に歌わせることを好んだことは知られていますが、ここでは歌詞のニュアンスを際立たせるため、各節を異なる歌手に割り当てています。
ジョン・ラターは1985年、ケンブリッジ大学セント・ジョンズ・カレッジのオルガン奏者兼聖歌隊指揮者だったジョージ・ゲストの招待で「There is a flower」を作曲した。歌詞は15世紀の司祭で詩人のジョン・オードレーによるもので、枝が新しい生命の兆しを示し、中世の絵画やステンドグラスによく描かれた「ジェシーの木」のイメージに焦点を当てている。メロディーは各詩節の中盤に向かって自然に上昇し、その後下降していく様子は、花が咲いては枯れる様子に似ている。ラターは、ソロの声部と6部和音の記譜を対比させながら、さまざまなテクスチャの旅へと私たちを誘う。特に効果的なのは第4詩節のオーケストレーションで、高音部では低音部のメロディーに合わせて「アレルヤ」を歌う天使の飛翔が表現されている。
500曲以上の作品が名を連ねるヤコブ・ヘンドルは、ルネサンス後期の多作な作曲家で、ボヘミアにおける対抗宗教改革の時代に作曲活動を行いました。祝祭的なモテット「カニテ・チューバ」は、印象的な下降モチーフで始まり、5つの下声部が次々と登場します。テクスチュアはしばしば忙しく複雑で、テキストの重要な瞬間を強調するために、時折2つまたは3つのパートが連結されます。金管楽器のファンファーレによく見られる旋律線は、「vocate(ヴォケート)」や「et clamate(エト・クラマート)」などの言葉に用いられ、福音を告げるトランペットの音を想起させます。
長さ6フィートを超える羊皮紙の巻物であるトリニティ・キャロル・ロールは、英語のポリフォニック・キャロルの最も古い資料です。15世紀初頭のイースト・アングリアで作られたこの巻物には、5線譜に中期英語とラテン語で書かれた13のキャロルの歌詞と楽譜が記されています。その中には、1415年にヘンリー5世がフランス軍に勝利したことを祝う愛国歌「Deo gracias Anglia!」(別名「Agincourt Carol」)や、後にベンジャミン・ブリテンが1942年に彼の「Ceremony of Carols」のために編曲した人気の「There is no rose」が含まれています。
「ヴェルブム・カロ・ファクトム・エスト」は、聖ヨハネ福音書冒頭の有名な受肉の物語を歓喜に満ちた曲に編曲したもので、クリスマスの朝課で歌われたと考えられています。ハンス・レオ・ハスラーによるこの6声楽のための曲は、1591年に彼の作品集『聖歌集』に初版が収録されました。ヴェネツィアの伝統に倣い、各声部は複数のグループに分かれ、音楽を互いに受け渡し、テキストのクライマックスで喜びに満ちた合唱へと導きます。作品の終盤、ハスラーは「et veritatis」において、3声と6声のテクスチャを猛スピードで交互に切り替え、神の真理の啓示を熱狂的に描き出しています。
16世紀に遡るイギリスのクリスマスキャロル、コヴェントリー・キャロルは、もともとマタイによる福音書のクリスマス物語を題材としたミステリー劇『羊毛刈り師とテイラーの祭典』の中で演奏されました。このキャロルの独特な歌詞は、ヘロデ王が2歳未満の男児を皆殺しにするよう命じた「幼児虐殺」に言及しており、死にゆく子供たちの母親たちが歌う子守唄の形式をとっています。
「我らが救世主の幼年時代について」は、2014年にオーウェイン・パークによって作曲され、フランシス・クオールズ(1592–1644)の詩『神の空想』に題材をとっています。声は豊かで曖昧な音色のタペストリーを織り成し、そこからソリストたちが徐々に姿を現し、彼らの幅広い感嘆の声は、合唱団のよりしなやかな和声進行と対照をなします。冒頭の和音は作品全体を通して繰り返し用いられ、「祝福された」や「微笑む」といったテキストの重要な場面を際立たせるために用いられます。
エレノア・デイリーによる美しい「クリスマスに愛が降りてきた」は、2004年にカナダ、トロントのヴィクトリア・スカラーズのために作曲されました。作詞はクリスティーナ・ロセッティで、彼女は1885年に『Time Flies: A Reading Diary』にタイトルのないこの詩を出版しました。テノール独唱者が、主に音階的な旋律を奏で始め、曲が進むにつれてこの旋律は発展していきます。「アレルヤ」の短い間投詞がハーモニーを様々な方向に揺らしますが、作品は粘り強く調性の中心へと戻り、温かく心地よい感覚を残します。
ミヒャエル・プレトリウスは、いくつかの作曲集に「In dulci iubilo」の旋律を収録しています。この旋律自体は、おそらく1400年頃にライプツィヒでドイツ語とラテン語でマカロニック・キャロルとして初めて記譜されたもので、「ガウデーテ」と同様に、1582年の「Piae Cantiones」集に収録されています。J.S.バッハはここでこの美しい旋律を、彼特有の明るい和声で奏で、同じテーマに基づいたオルガンのためのコラール前奏曲BWV751も作曲しました。
トーマス・ハーディの詩「牛たち」は、クリスマスイブがクリスマス当日へと移り変わる、静かな暖炉のそばの情景を描いています。期待感が漂う空気を、ジョナサン・ラスボーンは、なかなか落ち着かないハーモニーで紡ぎ出します。全体に豊かなテクスチャーと、声を通して一定のテンポが保たれ、まるで古代の物語が、うっとりとした聴衆に語りかけられているかのような感覚を与えます。
「Away in a manger(飼い葉桶の中の羊飼い)」の歌詞はかつてドイツの宗教改革者マルティン・ルターの作詞と考えられていましたが、現在では完全にアメリカ起源であると考えられています。おそらく最も有名な曲はウィリアム・ジェームズ・カークパトリックによるもので、ここではフィリップ・ローソンが編曲しています。第1節はシンプルな4部ハーモニーで、第2節と第3節ではゆっくりとしたハーモニーを背景にソロヴォイスが際立っています。
1857年秋に「One Horse Open Sleigh(馬の橇が一頭だけ)」というタイトルで出版されたジェームズ・ロード・ピアポントの『ジングルベル』は、もともと感謝祭シーズンに作曲されたが、たちまち12月の祝祭に祭り好きの人々に利用された。雪上を走る馬橇はほとんど音を立てないため、ニューイングランドの冬の季節には、見通しの利かない交差点での衝突を避けるため、馬具に鈴の付いたストラップを付けるのがよく行われていた。曲のリズムは速歩する馬の鈴の音を模倣しているが、ゴードン・ラングフォードは時折、標準的な拍子から少し逸脱し、祝祭の韻律にシェリー酒の風味を少し加えている。
トラックリスト
Tracklist:
- Veni Emmanuel
- Nun komm der Heiden Heiland a 6
- The Annunciation
- Videte miraculum
- The Promised Light of Life
- Gaudete
- The Truth Sent from Above
- Es ist ein Ros' entsprungen
- Angelus ad virginem
- Lullay My Liking H. 129
- There Is a Flower
- Canite tuba
- There Is No Rose
- Verbum caro factum est
- Coventry Carol
- On the Infancy of Our Saviour
- Love Came Down at Christmas
- In dulci iubilo
- The Oxen
- Away in a Manger
- Jingle Bells
オーディオプレビュー
オーディオ プレビューには、レコードや CD リリースには含まれていない追加の曲や異なる曲が含まれている場合があります。
レビュー
配送と返品
SHIPPING
- In-stock items generally ship within 24 Hours
- Free shipping on orders over $50.
- International delivery time - 10-14 business days in most cases
- Easy 30 days returns and exchanges
RETURNS
If there is an issue product you can return it within 30 days. To start a return, please fill out our RETURN REQUEST FORM.

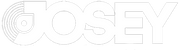
 ジョージーTシャツ&帽子
ジョージーTシャツ&帽子 セレクターレコードバッグ
セレクターレコードバッグ ジョージー限定
ジョージー限定 スカイラークソウル株式会社
スカイラークソウル株式会社 









